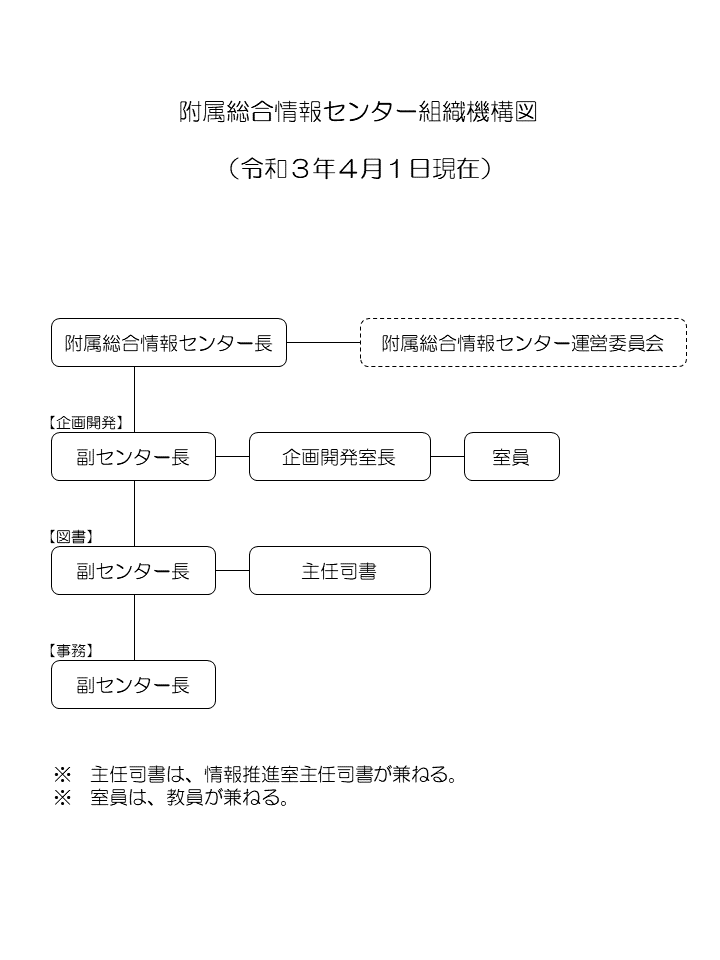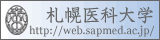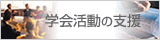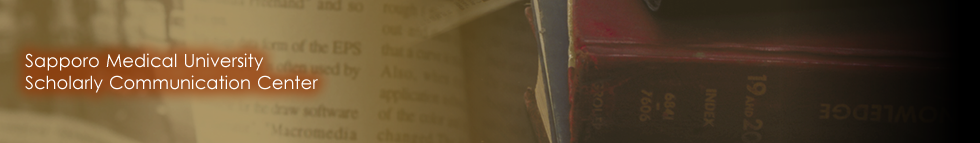
ご案内
北海道内医療機関等発行誌の電子化支援
北海道内医療機関等発行誌の電子化支援
北海道内医療機関等発行誌の電子化サービスとは病院誌、年報等の発行を行っている道内医療機関等で、発行誌全文の電子化を希望する機関等に対し、電子化を行う上での技術的助言を行い、かつ作成された電子化資料の預託を受け、代行してインターネット上で公開するためのサービスです。
病院誌等、一般の商業ルートでは販売されず、入手しづらい資料を総称し、図書館専門用語では「灰色文献(Grey literature)」と呼びますが、それらの資料を電子化し、検索機能を付与して公開することは学術情報の流通を推進する上で非常に意義のあるものと考えます。
公開までの手順
- 電子化による公開を希望する医療機関等(以下、「医療機関等」と略す)は対象誌に収載されて
いる記事等について執筆者本人より著作権許諾を受諾する。
- 医療機関等は当該誌の印刷段階で、PDF(*)により電子化データを作成する。
- 医療機関等における上記②の作業執り進めに対し、札幌医科大学は附属図書館を通じ、技術的
助言を行う。
- 医療機関等は作成したPDFデータを札幌医科大学附属図書館へ送付する。
- 札幌医科大学附属図書館は送付されたPDFデータよりタイトル、著者名、抄録等の検索データを
作成するとともに、札幌医科大学学術機関リポジトリ「ikor(イコル)」への登録によりインターネットを通じ公開を行う。
- 札幌医科大学附属図書館は医療機関等の独自システムによる電子化資料の公開に対し、上記
作成の作業によって蓄積されたデータを返納するとともに、独自システムによる公開に対し、助言と支援を行う。
(*)PDFとはAdobe社が開発した電子出版形式で「Portable Document Format」の略。
利用条件等
- 道内医療関係機関等に限ります。
- 公開対象資料は医療機関等において著作権の許諾を受けた逐次刊行物資料全文に限ります。
- 記念誌等の単行資料、逐次刊行物であっても一部の記事のみの公開希望は対象となりません。
- 電子化データであるPDF作成のための諸経費は医療機関等のご負担となります。
お問い合わせ先
本サービスに関し、ご不明な点等がございましたら総合情報センター図書係(内線24160、E-mail: satuisi@sapmed.ac.jp)までお問い合わせください。
沿革
| 平成18年4月 | 基礎医学研究棟に、旧附属情報センターと旧附属図書館との統合により附属総合情報センターを組織 |
旧附属情報センターの沿革
| 平成2年9月 | 学内に設置した札幌医科大学将来構想検討委員会でまとめた「21世紀に向けた札幌医科大学の課題」の中で、北海道における医学、医療の教育研究の拠点としての役割を果たすため、従来の図書館の概念を越えた「情報センター」が必要とされた |
| 平成3年9月 | 札幌医科大学情報化推進委員会が「札幌医科大学情報化推進基本方針」を作成し、情報通信ネットワークシステムを兼ね備えた全学的な情報化システムの考え方、整備計画を具体化し、附属病院における診療業務から経営管理業務まで一連の業務を総合処理する「医療情報総合システム」や医学教育システム、ネットワークシステムを開発、整備し運用 |
| 平成5年9月 | 札幌医科大学情報センター棟検討委員会において、「札幌医科大学附属情報センター整備に関する基本計画」を作成 |
| 平成8年5月 | 札幌医科大学情報センター整備準備室において、「情報センターの整備の基本方針」を作成し、情報センターの整備理念、情報センターの基本的機能の概要を取りまとめた |
| 平成9年3月 | 基本方針に基づき、具体的なシステムの調査分析を行い、「札幌医科大学情報ネットワークシステム基本構想」を策定 |
| 平成9年11月 | 「札幌医科大学情報ネットワークシステム基本設計書」策定 |
| 平成10年3月 | 経済産業省「先進的アプリケーション基盤施設整備事業」を活用し、臨床教育研究棟、附属病院の学内ネットワークのインフラ、地域医療支援機器、サーバ機器等整備、当時最先端のギガビット・イーサネットの技術を先駆けて活用 |
| 平成10年12月 | 地域医療支援機器DxMM等の導入 |
| 平成11年3月 | 基礎医学研究棟、保健医療学部棟の学内ネットワークのインフラ整備。サーバ群を基礎医学研究棟5階中央サーバ室に集約 |
| 平成11年4月 | 基礎医学研究棟に、附属情報センターを組織 附属情報センターホームページ開設 |
| 平成11年9月 | 中央サーバ室内のサーバ機器の充実 |
| 平成11年10月 | 教育支援機器を、基礎医学研究棟5階(Mac端末50台他)及び保健医療学部棟1階(Windows端末50台)のコンピュータ実習室内に整備 |
| 平成12年3月 | 地域医療支援機器DxMM、Viewsendなどの充実 |
| 平成12年6-7月 | 情報G7の取り組みの一環として、附属情報センターと解剖学第一講座共同で、本学と米国国立医学図書館間を、通信衛星等を介した高速通信実験、地上線との経路変換実験を行い成功、通信実験関係者に対し、NASAから感謝状が授与された |
| 平成12年11月 | 研究支援機器を、基礎医学研究棟5階情報研究室内に整備 |
| 平成13年2月 | ネットワーク端末機器を、学内の80の所属に整備 |
| 平成13年10月 | 平成13年10月 附属情報センターと内科学第一講座共同で、10月17日から19日まで京都国際会議場で開催されたDDW2001(日本消化器病学会学術講演会)をJGN(JapanGigabitNetwork)の光ファイバーを用いて、会場と本学、琉球大医学部、東京医科歯科大学等を結びリアルタイム中継に成功(日本消化器病学会等との共同研究の一環) 本学からさらに専用回線により札幌市内及び空知管内数カ所の病院に再配信(次世代インターネットプロトコルIPv6を活用) |
| 平成14年3月 | サーバ室内に、コンピュータ・ウイルスチェックサーバ及び統計解析用サーバ整備 |
| 平成16年2月 | 地域医療支援機器の老朽更新 DxMMの他、新たなニーズに対応するため、TV会議システム等も整備 |
| 平成16年2-3月 | 平成10~11年にかけて整備した学内ネットワークインフラの老朽更新。安定性、セキュリティを重視したネットワーク構成、バックボーンは10GB、障害時に迂回可能な冗長構成 |
| 平成16年10月 | 札幌医科大学情報セキュリティポリシー策定 教育支援システム機器の更新(MacOSXからWindowsXPへ) |
| 平成16年11月 | JGNⅡ(JapanGigaNetwork2:研究開発用ギガビットネットワーク)に参加(ME学会中継(愛媛県―札医大) |
| 平成17年3月 | 東棟・本務棟LAN機器の更新 地域医療支援システム端末機器の更新(遠隔CPCシステム運用開始) |
| 平成17年7月 | 高速リモートアクセスサービス(VPN)運用開始 |
| 平成17年9月 | 迷惑メール対策サーバ運用開始 |
| 平成17年11月 | 研究支援システムの更新(遺伝子情報解析システムほか導入) |
旧附属図書館の沿革
| 昭和25年4月 | 旧女子医学専門学校校舎の一室に事務室、閲覧室及び書庫を設置、業務を開始 |
| 昭和28年1月 | 基礎医学校舎第1期工事落成に伴い、衛生学教室の一部を借用移転 |
| 昭和28年7月 | 病理学教室標本室に移転 |
| 昭和31年7月 | 附属図書館新築落成 |
| 昭和34年3月 | China Medical Board of New York(CMB)理事長O.R.マッコイ博士来学、図書館視察 |
| 昭和34年5月 | CMBより設備費に5,000ドル、図書館整備費に10,000ドルの援助、以後、昭和43年まで合計40,260.70ドルの援助 |
| 昭和34年10月 | CMB援助による書架(書庫3階)、リフト完成(9.15着工) |
| 昭和37年9月 | 昭和36年12月 1日CMBより増改築費として援助を受けた増築工事落成(37.6.1着工) |
| 昭和40年6月 | 医学英語テープ・ライブラリー開設 CMBコンネル博士来館視察 |
| 昭和41年3月 | CMB理事長O.R.マッコイ博士来館視察 |
| 昭和41年7月 | 第37回日本医学図書館協会総会を当番館として本学において開催 |
| 昭和42年8月 | CMBコンネル博士来館視察 |
| 昭和43年5月 | 文部省公立大学設備整備等補助金による学生参考図書の充実に着手 45年度までに道費を合わせて、7,214,000円、1,187冊整備 |
| 昭和43年9月 | CMBコンネル博士来館視察 |
| 昭和44年7月 | 第4回医学図書館職員研究集会東日本集会を本学において開催 |
| 昭和46年8月 | 第6回医学図書館職員研究集会東日本集会を本学において開催 |
| 昭和46年12月 | 「札幌医科大学附属図書館利用内規」制定 |
| 昭和47年6月 | 進学課程図書館を元第1自習室に移転し、図書館分室として運営開始 |
| 昭和55年8月 | 医学文献検索オンラインシステム導入 |
| 昭和61年3月 | 「札幌医科大学附属図書館利用規程」制定 |
| 昭和62年4月 | 昭和62・63年度公立大学協会図書館協議会会長館 第19回(昭和62年度)総会を札幌市において主催(昭和62年5月29日) 第20回(昭和63年度)総会を札幌市において主催(昭和63年6月 3日) |
| 平成2年3月 | 札幌医科大学情報センター検討委員会より「札幌医科大学情報センター基本構想(案)」答申 |
| 平成3年3月 | 札幌医科大学情報センター検討委員会より「札幌医科大学情報センター基本計画書(案)」答申 |
| 平成3年4月 | CD-ROM(Medline)による情報検索サービス開始 |
| 平成4年3月 | 札幌医科大学学術振興会よりCD-ROM(医学中央雑誌)の助成を受ける 6月29日より情報検索サービス開始 |
| 平成5年4月 | 札幌医科大学衛生短期大学部図書室を保健医療学部分室として運営開始 |
| 平成6年4月 | 学術情報センターと接続 |
| 平成6年5月 | 文献目録所在情報入力開始 |
| 平成7年6月 | 仮図書館建設工事着工 |
| 平成8年3月 | 仮図書館落成 |
| 平成8年5月 | 仮図書館に移転し業務開始 |
| 平成8年10月 | 学内LAN経由でMEDLINE・医学中央雑誌の検索開始 |
| 平成8年10月 | 新棟建設工事着工 |
| 平成 9年10月 | 図書館システム(リコー製LIMEDIO)導入 札幌医科大学附属図書館ホームページ開設 |
| 平成11年1月 | 基礎医学研究棟竣工 |
| 平成11年4月 | 医学部及び保健医療学部分室の廃止 |
| 平成11年6月 | 新図書館開館 IDカードによる24時までの特別開館(無人開館)を開始 Ovid/OPAC/ILL連動システム運用開始(国内初) |
| 平成12年4月 | 平成12年度公立大学図書館協議会会長館 第32回(平成12年度)総会を札幌市において主催(平成12年6月2日) |
| 平成12年5月 | 第71回日本医学図書館協会総会において、本学図書館システムが日 本医学図書館協会賞を受賞(受賞論文:Proxyサーバを使った異種データベース間連動システムの開発) |
| 平成13年5月 | 医学中央雑誌Web版検索システム「MEDOC-J」運用開始(国内初) |
| 平成14年4月 | NACSIS-IR(国立情報研究所日本語情報検索サービス)提供開始 |
| 平成14年 7月 | 道内地域医療関係者等に対するPUBMED仲介による文献複写申込みサービスを開始 道内医療機関発行誌の電子化支援サービス開始 |
| 平成14年12月 | 本学卒業生をはじめ道内医療従事者への米国国立医学図書館「PubMed」との機能連携によるインターネットを介した学術文献複写受付サービスの提供開始(アジア初、世界9番目) |
| 平成15年4月 | 電子ジャーナル導入による学術雑誌学内一誌化を推進 |
| 平成16年4月 | 祝日開館(特別開館)を開始 |
| 平成17年 2月 | 本学卒業生をはじめ道内医療従事者へのNDL-OPAC(国立国会図書館雑誌記事索引)仲介による学術文献複写受付サービスの提供開始(国内初) |